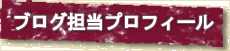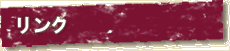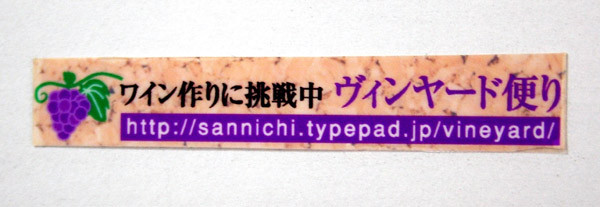納会
ヴィニュロンズクラブの納会がこのほど、甲府市下石田の「カフェ・ラ・トゥーシェ」で開かれました。メンバー22人が出席。冒頭、中村一政専務(山梨放送)から「畑のブドウ樹は落葉し、休眠状態に入りました。お疲れ様でした」とのあいさつがありました。ワインと料理を楽しみながら、来期のさらなる奮闘を誓いました。
この日は畑作業への出席状況に応じて加算する今期の獲得ポイントの発表がありました。上位者(筆者を除く)は、中村専務を筆頭に、野口英一社長、飯田圭滋さん(山梨放送)、奈良田伸司さん(山梨文化会館)、藤木教行さん(山梨放送)でした。
また、メンバー限定のPR用シールのニューバージョンが配布されました。デザインはそのままに、素材が透明シートに改良されました。会社の名刺に張って活用します。
この日も、赤ワインはもちろんメルローが主役となりました。
ワインリストは次の通り。
▽クレマン・ダルザス(ルネ・フレイツ・エシャール)
▽クレマン・ド・ブルゴーニュ(レ・ヴィニュロン・ド・オート・ブルゴーニュ)
▽シャルドネ&甲州2007無濾過(メルシャン)
▽千野甲州2007(旭洋酒)
▽メルロー&マスカット・ベリーA2006無濾過(メルシャン)
▽マーガレットリバー・メルロー2005(ファーモイ・エステイト)
▽コート・ド・カスティヨン2004(シャトー・デギュイユ)
2008年12月05日|個別ページ



 標高
標高