マルチ敷き
4月から新たに部員が加わり、総勢34人になったそうです。3月28日はマルチ敷きの作業がありました。当日は8人が参加したとのことです。マルチは昨年敷きましたが、耐用年数の長いものということで、厚手のマルチに張り替えることとなりました。すでにブドウ樹が植えてあるので、2枚のマルチを畝(うね)の真ん中で貼り合わせます。なかなか作業が思うように進まず、マルチ敷き初日は15畝中3畝までしか仕上がらなかったそうです。
以下は作業の様子です。
2009年04月09日|個別ページ

 標高
標高 栽培
栽培 栽培品種 メルロー(約900本)
栽培品種 メルロー(約900本) 栽培品種 シャルドネ(約900本)
栽培品種 シャルドネ(約900本) 栽培品種 シャルドネ(約490本)
栽培品種 シャルドネ(約490本)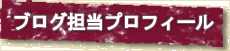
4月から新たに部員が加わり、総勢34人になったそうです。3月28日はマルチ敷きの作業がありました。当日は8人が参加したとのことです。マルチは昨年敷きましたが、耐用年数の長いものということで、厚手のマルチに張り替えることとなりました。すでにブドウ樹が植えてあるので、2枚のマルチを畝(うね)の真ん中で貼り合わせます。なかなか作業が思うように進まず、マルチ敷き初日は15畝中3畝までしか仕上がらなかったそうです。
以下は作業の様子です。
2009年04月09日|個別ページ
山梨県ワイン酒造組合の「若手醸造家・農家研究会」(武井千周代表)は、山梨大甲府キャンパスで、3回目となる官能評価勉強会を開きました。締めくくりとなる今回のテーマは「ワインのブーケ」。ブーケは第3アロマと呼ばれる熟成由来の香りです。講師はメルシャン勝沼ワイナリーの鷹野永一さん。
今回も前回同様にサンプルを並べ、香りを確かめました。
以下、サンプルを紹介します。
▽ダイアセチル(バター香)
▽オイゲノール(クローブ香)
▽バニリン(バニラ)
▽ウイスキーラクトン(ココナッツ香、スパイシーなセロリ)
▽ソトロン(カレー香、メープルシロップ、キャラメル、こがし砂糖)
▽揮発性フェノール4種類(4-ビニルフェノール、4-ビニルグアイヤコール、4-エチルフェノール、4-エチルグアイヤコール)
オイゲノール、バニリン、ウイスキーラクトンは樽(たる)由来とのことでした。
2009年03月24日|個別ページ
14日は枝の誘引をしました。午前中は雨だったので、午後からの作業。強風が吹きすさぶ肌寒い一日でした。
剪定(せんてい)した枝をワイヤに結びつけていきます。一本一本、地道な作業です。
下草を刈る乗用草刈り機が導入されました。昨年を思うと、これからは「草との闘い」だった気がしますが、何とも心強いです。
ボロボロになったマルチを後日張り替えるため、この日はマルチをはがす作業もしました。
写真左は誘引前、右は誘引後です。あとは萌芽を待ちます。
前日とは一転、晴れ間が広がった15日。畑の消毒をしました。木の根元の草も取り除きました。
2009年03月16日|個別ページ
2月の休日に、都内で開かれたブルゴーニュワインのセミナーに参加する機会がありました。ブルゴーニュ・マランジュ(村名AOC)から、「ドメーヌ・シュヴロ」オーナーの(※)パブロさん、(※)かおりさん夫妻が来日しているのに合わせ、米国ワインエデュケーター協会日本支部(児島速人支部長)が開きました。テーマは「環境にやさしいブドウ栽培」です。
パブロさんは、数年前に山梨を一度訪れたことがあるとのことでした。このドメーヌの「SAKURA」というロゼワインはお花見にぴったりだと思っていますが、パブロさんの明るい人柄に、あらためてワインに関心を持つようになりました。
パブロさんと話をすると、「マンズワインの武井千周さんと親交がある」。記者はすかさず「武井さんから指導を受けて会社の畑でメルローの栽培に取り組み、いずれワインにします。その様子を紹介しているホームページもあります」と説明しました。夫妻は大変興味を持たれたようでした。
さて、ドメーヌ・シュヴロは近年、有機栽培への移行を進め、化学合成製品の使用を一切中止したとのことです。セミナーでは、取り組みを進める「環境農業」を中心に説明や解説がありました
環境農業は自然環境への配慮を重視しますが、そのためには「ブドウ栽培に対する高等な知識や技術、頻繁な観察、惜しむことのない労働が必要」と話していました。害を与える生物への防止策としては、昆虫類では「天敵」の役割など生物の多様性を挙げ、菌類では摘芯などの予防措置の重要性を指摘。菌類では薬草の説明もあり、例えばうどんこ病に対し、発芽から開花期までの間ならば浸漬したイラクサなどが有効としていました。
まとめに「環境農法で造ったワインは、より多くの味わいを持つ」と強調していました。
最後に、ドメーヌ・シュヴロのアリゴテ、ピノ・ノワール計5種類のワインをテイスティングしました。いずれも繊細で、やさしい印象を持ちました。このうち、「マランジュ・シュール・ル・シェーヌ2006年」(ピノ・ノワール100%)はパブロさんが言うとおり、「すき焼きワイン」として試したくなりました。
※パブロさん 2002年7月からドメーヌ(家族経営、長男)のワイン造りに参加。03年からは醸造家の傍ら、ボーヌの国立農業・醸造職業学校(CFPPA)で非常勤講師として醸造学を教えている。
※かおりさん 航空会社在籍中にシニア・ソムリエを取得し、ボルドー大学醸造学部に留学。03年にパブロさんと結婚。06年にブルゴーニュ大学付属IUTシャロン・シュール・ソーヌ校でワイン・ビジネスの修士号を取得。現在は、主に輸出業務の担当。
2009年03月03日|個別ページ
山梨県ワイン酒造組合の「若手醸造家・農家研究会」(武井千周代表)は、山梨大甲府キャンパスで、2回目となる官能評価勉強会を開きました。今回のテーマは「ワインのアロマ」。講師は甲州市勝沼町の丸藤葡萄酒工業、安蔵正子さん(ボルドー大学・ワイン利酒適正資格取得)です。
ワインの香りは、ブドウ由来の「第一アロマ」と、発酵由来の「第二アロマ」、熟成由来の「第三アロマ(ブーケ)」に分けられます。今回は第一、第二について学びました。8種類のサンプルがテーブルに並び、実際に香りを確かめました。
以下は8種類のサンプルです。
▽第一アロマ
・ゲラニオール(バラの香り)
・リナロール(ラベンダーの香り)
・シトロネロール(レモンの香り)
・アントラニル酸メチル(※ラブルスカ種・※フォクシーフレーバー)
・β-イオノン(スミレの香り)
・β-ダマセノン(焼リンゴ、南国のフルーツの香り)
▽第二アロマ
・3MH=3-メルカプトヘキサノール(グレープフルーツ、パッションフルーツの香り)
・IAA(エステル)酢酸イソアミル(バナナの香り)
サンプルを使って特定の香りだけを確認する作業は、とても貴重な経験でした。「β-イオノンは遺伝的にかげない人がいて、その数も結構多い」(安蔵さん)とのことでしたが、記者にとっても非常にかぎ取りにくい香りでした。でも、スミレの香りって赤ワインでよく使っていますが、その根拠は何によっているのでしょう…。
今回は、ワインのテイスティングも充実していました。テーマは3人の醸造家が感動したワイン。その銘柄を紹介いたします。
▽ラシーヌ(ロワール、クロード・クルトワ氏のワイン)=小山田幸紀氏(ルミエール)
▽ニコラス・カテナ・サパータ(アルゼンチン・メンドーサ)=渡辺直樹氏(サントリー登美の丘ワイナリー)
▽ラ・フルール・ペトリュス(ポムロール)=武井千周氏(マンズワイン)
※ラブルスカ種 アメリカ系ブドウ
※フォクシーフレーバー ヨーロッパ人の好まない香り
2009年02月23日|個別ページ
花粉が飛び舞う15日。丹精込めてブドウを育てるため、畑で黙々と作業をしました。
まずは「枝磨き」です。剪定(せんてい)ばさみで、過日切り残した枯れ枝などを除去し、枝をきれいに整えていきます。
芽のわきから伸びた小さな枝が結構多かったです。
このところのぽかぽか陽気が影響してか、枝の切り口に樹液をじんわりとにじませる枝も見られました。
そして、発芽促進剤「メリット青」を芽に塗布。鉛筆大の太さの長梢に的を絞り、芽吹きやすい先端から2芽を飛ばして、ローラーをかけていきました。
備忘録として、昨シーズンのカレンダーをこのブログをもとにまとめてみました。
▽発芽 4月20日ごろ
▽展葉 4月28日ごろ
▽開花 6月6日ごろ
▽ベレーゾン初め 7月31日
▽ベレーゾン 8月3日
2009年02月18日|個別ページ
今年もいよいよ作業が始まりました。7日に剪定(せんてい)を行いました。冬季の剪定は、果実が付く芽の数を限定するのが目的となります。
マンズワインの中山正男さん(写真左・中央)と、武井千周さん(写真右・左)に指導していただきました。
昨年伸びた枝を間引いていきますが、2シーズン目の今年は「長梢(ちょうしょう)剪定」にするとのことです。昨年の若枝が伸びたのが「長梢」。残す枝を見極めていくのですが、実際にやってみると「どこをどう切ればいいの?」と頭を悩ますことばかりです。ちなみに、この長梢を短く剪定し、2芽にしたのを「短梢(たんしょう)」と言いまして、本格的に収穫する3年目以降は「短梢剪定」にするそうです。
剪定ばさみの「シャキ」「シャキ」という音が心地よく畑に響きます。鉛筆より明らかに細い枝は2芽ほど残して、思い切って切り落としました。今年の成長に期待をかけます。
剪定した枝の片付けも大切な作業です。
短梢剪定は作業のしやすさが利点です。中山さんからは「ブドウの枝は先端にいくほど優勢となりますが、メルローはその傾向が顕著です。裏を返せば、先端以外はあまり芽吹きがよくないのです。でも、短梢のように2芽しか残さなければ、必ず芽は出てきます」と、教えていただきました。メルロー栽培=短梢剪定に納得です!
下の写真は枝先の2芽以降で芽吹きをよくするための方法だそうです。
「3月上旬ごろまでに、芽の先5ミリ程度のところに芽傷を入れます」と中山さん。上の写真の中央辺りに「芽傷」がありますが、確認できますでしょうか。特に枝ぶりが強い場合には、2月にメリット青2倍液を芽に塗布する方法もあるそうです。
ボクトウガの被害を受けた枝を発見しました。枝の途中が根のような状態になっています。これは迷わず、切り落とします。
甲府は2月に入ってから暖かい日が続いています。この日はお昼をはさんでの作業でしたが、外で弁当と豚汁を食べるのにちょうどいい陽気でした。
剪定も終わり、ブドウ畑もさっぱりしたように見えます。
2009年02月10日|個別ページ
山梨県ワイン酒造組合の「若手醸造家・農家研究会」(武井千周代表)がこのほど山梨大甲府キャンパスで開いた、ワインの官能評価勉強会に参加しました。
テーマは「ワイン中のオフフレーバー(異臭・異味)」。甲州市勝沼町のワイナリー、中央葡萄酒の三沢彩奈さんが講師を務めました。
オフフレーバーの原因別に種類が分類され、大変分かりやすい講義でした。9種類の水溶液を実際に使って、においをかぎ分ける実習もありました。
以下、オフフレーバーを紹介します。
▽ブドウの熟度不足
・ヘキサナール(ハーブ、野菜臭)
・メトキシピラジン(ピーマン臭)
▽微生物汚染・醸造管理
・酢酸(お酢)
・酢酸エチル(セメダイン)
・アルデヒド(青リンゴ様)
・ジオスミン(カビ、土臭)
・TCA(コルク、カビ臭=※ブショネ)
▽揮発性硫黄化合物(原因:残留農薬、SO2、窒素・酸素不足)
・メチオノール(キャベツ、カリフラワー臭)
・エタンチオール(タマネギ、ニンニク臭)
三沢さんは「メトキシピラジンは畑での努力でなくしていけるにおい」「TCAは不衛生だと増え、醸造家のモラルの問題」「醸造家がオフフレーバーを認識するのは大事だが、目的ではない」と解説。武井代表は「においの苦手な分野を知るのは大切」と話していました。
※ブショネ コルク製造時に漂白に使われる塩素がもとでトリクロロフェノールが作られ、この物質がカビと結合すると、トリクロロアニソール(TCA)が発生する。コルクのカビのようなにおいがワインにも伝染し、味わいにも影響する
2009年02月03日|個別ページ
本年も頑張って、畑のレポートはもちろん、ワインについてのトピックを含めて更新していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
現在のブドウ園の様子です。1年のサイクルの中では休眠期にあたります。このところ甲府は最低気温が氷点下と、厳しい寒さが続いています。
下の写真は休眠芽です。
ブドウ樹はマイナス12~13度までは凍害にならないとされています。ただし、根は耐寒性が弱くマイナス4度まで。もちろん、根はある程度の深さに分布していますが、地表に近い5センチ程度の所にはほとんどないそうです。山梨大での植物学の講義を取材した際に聴きました。
2009年01月16日|個別ページ
畑の木々も、すっかりと落葉しました。
10日にマンズワインの中山正男さんが双葉農場を視察され、1年間の総括と来年の作業について指導をしていただきました。
当日立ち会った中村一政専務(山梨放送)によりますと、中山さんは総括として「ブドウの木は順調に生育しており、節と節の間が短く、いくつか幹を切断して髄の様子もチェックしてみたが、問題ない」とのことでした。
そして、「この状態で病気にかからないようにすれば、来年は半作(予想最大収穫量の半分)の収穫(約500キロ)ができて、仕込めるでしょう」と、うれしい言葉がありました。
2008年12月16日|個別ページ
記事・写真・イラストの無断掲載・転用を禁じます。Copyright 山梨日日新聞社 THE YAMANASHI NICHINICHI SHIMBUN.