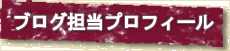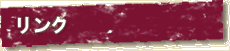ラインガウ甲州2007
日本固有の品種である甲州種ブドウが、ドイツの中でもワインの有力産地ラインガウで栽培されています。収穫3年目の2007年ヴィンテージを試飲する機会がありました。
このほど、甲府市桜井町のレストラン・ボルドーで開かれた「ラインガウ甲州ワインの夕べ」に参加しました。「ラインガウ甲州」の06年、07年の比較がメーンです。
ワイナリー関係者も多く参加していましたが、そのコメントからは07年の人気が高く、個人的にも同様に思いました。07年はバランスのとれた「辛口」ですが、トロピカルフルーツなど06年よりも際だった香りや、完熟したブドウの味わいなどに特徴があるように感じました。
醸造元ショーンレーバーさんも「過去最高の出来栄え」とコメントしています。
07年の収穫は、例年よりも2週間遅い11月16日(気温は朝マイナス5度、収穫時0度)。収穫ブドウの糖度はブリックスで21.5度ということです。
2007年1月、ドイツ・ラインガウに取材に行った時の写真です。甲州種ブドウの畑は、ライン川を望む傾斜地の特級畑の一画にあり、いわゆる“VIP待遇”です。
2008年09月11日|個別ページ



 標高
標高