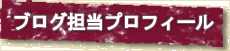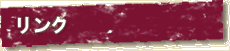植物は正直?
畑を回ってみて気が付くのは、北側の木が目立って成長著しいことです。


撮影は、7月5日。同じ時期に苗木を植えましたが、片方は2メートル近く、もう片方は50センチ程度です。木の特性の違いもあるかもしれませんが、北側はかつて野菜畑だった場所とのことで、まだ肥料が効いているのかもしれません。草むらだった場所の方がゆっくり育っていることを考えると、植物は正直と言えそうです。
生食用と違い、醸造用ブドウの木は成長が良すぎるのも考え物。徒長すると管理が大変ですし、マンズワイン・武井さんは「(配合肥料に含まれている)窒素が多いと着色に好ましくない」と指摘していました。着色は赤ワインにとって、重要な要素です。
さて、7月5日は全体作業の日でした。


引き続き、誘引と草刈りに汗を流しました。気温が高くなるにつれ、体力消耗も早く、これからは暑さとも戦わなければなりません。

台木から芽が出ていたので、取り除きました。
台木は2種類使っていますが、木の場所からリパリア種とベルランディエリ種(いずれもアメリカ系)の交配種「5BB」の葉と茎と考えられます。穂木であるメルローはヴィニフェラ種(ヨーロッパ系)。まったく違う雰囲気があります。
2008年07月09日|個別ページ



 標高
標高