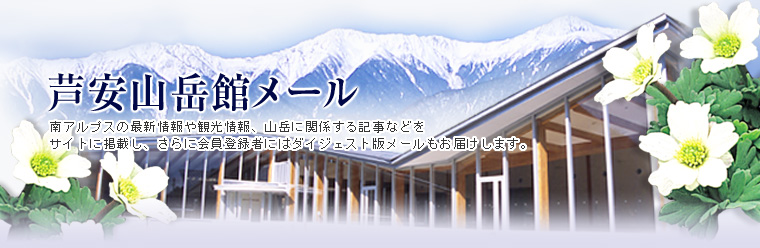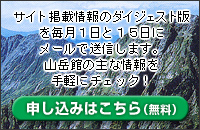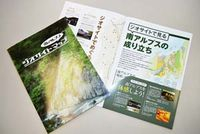まだまだ寒さの残る芦安-。春を探して散歩に出掛けると、新芽の鮮やかな緑色が印象的な「ふきのとう」=写真右上=を今年初めて、小曽利 (こぞうり)地区で見つけました。
まだまだ寒さの残る芦安-。春を探して散歩に出掛けると、新芽の鮮やかな緑色が印象的な「ふきのとう」=写真右上=を今年初めて、小曽利 (こぞうり)地区で見つけました。
この光景を写真撮影していると近所の人が、近くにある六地蔵様のかわいい姿も撮って行ったら、と言って案内してくれました。そこには、南天の木に包まれた高さ38センチの「六地蔵尊」=写真右下=が祭られていました。
 人間が現世から来世に渡ったとき、人間界での生き方により、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六道に分けられ、それぞれの道で現世の償いをしなくてはならないとされています。六地蔵は六道の入口に一体ずつ立って、地獄・餓鬼・畜生の三悪といわれる道に落とされ、厳しい責め苦にあっている者にも救いを施してやろうという、慈悲を表している仏であるといわれます。このため、人々は現世にあるうちにこれを祭り、来世での苦難から逃れられるようにと、真剣な祈りを捧げたそうです。また、日常の苦痛や災難から解放されるという、ありがたい仏であるともいわれ、信仰はさらに盛んになったそうです。
人間が現世から来世に渡ったとき、人間界での生き方により、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六道に分けられ、それぞれの道で現世の償いをしなくてはならないとされています。六地蔵は六道の入口に一体ずつ立って、地獄・餓鬼・畜生の三悪といわれる道に落とされ、厳しい責め苦にあっている者にも救いを施してやろうという、慈悲を表している仏であるといわれます。このため、人々は現世にあるうちにこれを祭り、来世での苦難から逃れられるようにと、真剣な祈りを捧げたそうです。また、日常の苦痛や災難から解放されるという、ありがたい仏であるともいわれ、信仰はさらに盛んになったそうです。
◆里山植物
ふきのとう(キク科・フキ属)
・フキの花のつぼみです。
・雪解けを待たずに顔を出します。
・湿気の多いところを好みます。
・春を代表する山菜です
・天ぷらや酢みそあえなどにして食べると、少しほろ苦くとてもおいしいです。