2025VT最後の全体作業
9月27日は、2025ビンテージ(VT)最後の全体作業でした。防鳥ネットの片付け作業です。撮影は、前島憲彦農場長と秘書室です。16人が3班に分かれて作業、3時間で撤去を終えました。2日間の作業を予定していましたが、1日で終了しました。1年間お疲れさまでした。
2025年09月27日|個別ページ

 標高
標高 栽培
栽培 栽培品種 メルロー(約900本)
栽培品種 メルロー(約900本) 栽培品種 シャルドネ(約900本)
栽培品種 シャルドネ(約900本) 栽培品種 シャルドネ(約490本)
栽培品種 シャルドネ(約490本)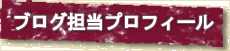
9月27日は、2025ビンテージ(VT)最後の全体作業でした。防鳥ネットの片付け作業です。撮影は、前島憲彦農場長と秘書室です。16人が3班に分かれて作業、3時間で撤去を終えました。2日間の作業を予定していましたが、1日で終了しました。1年間お疲れさまでした。
2025年09月27日|個別ページ
9月13、14の両日はレインカットの片づけ作業でした。
画像は13日の作業の様子です。NNSの相山哲也局長の撮影です。
13日の参加者は14人。ビニールを外してフレームに干すまでをしました。時折小雨が降る中の作業でした。
14日は11人。ビニールをたたむ作業をしました。ビニールが濡れないように地面に置かず、つるした状態で折りたたみました。
防鳥ネットの片づけを後日行います。
2025年09月13日|個別ページ
8月30日、今季の集大成である収穫を迎えました。シャルドネ、メルロの同時収穫は2年ぶり。シャルドネの収穫は昨年より5日遅く、メルロは8日早くなり、収量はシャルドネが1,370キロ(昨年比630キロ減)、メルロが1,040キロ(同250キロ増)でした。今季は3、4月に平均気温が例年より高く推移。5月は下旬に日照時間が平年よりかなり少なかったものの、6~8月は甲府の平均気温が各月として過去1番目に高く、記録的な猛暑となりました。ただ、8月はお盆前からお盆にかけて甲府の最低気温が一時的に下がり、昼夜の寒暖差が生まれて着色や糖度の上昇が進みました。また、8月の甲府の降水量は平年よりかなり少なくなり、全体的に粒が小さく、房も小ぶりの傾向となりました。シャルドネ、メルロとも糖度が20度を超え、過去最高レベルのブドウの出来でした。
仕込み時の分析値は下記の通りです。
◆シャルドネ
比重 1.090
糖度 21.80%
pH 3.55
総酸 4.90g/l
◆メルロ
比重 1.089
糖度 21.53%
pH 3.48
総酸 4.60g/l
収穫はまずメルロから。作業には30人ほどが参加し、バインド線外しから始め、4時間ほどで終わりました。シャルドネ、メルロとも全体的に病果や未熟果も少なく、スムーズに作業が進んだ印象です。
メルロ、シャルドネとも一粒口に入れてみましたが、甘みはもちろん、酸もまだしっかりと残っているのを感じました。朝食を挟んでシャルドネの収穫に移りました。二回目の全体休憩では、中村一政名誉農場長からスイカの差し入れがありました。今年は、全体的に房が小ぶりなのもあってか、収穫箱がかなりの数余りました。
2025年08月30日|個別ページ
8月2日は作業の山場、レインカットのビニール張り。暑さ対策として午前5時から作業を始め、予定の10時半より1時間早く終えることができました。ちなみに、この日の甲府は39.6度まで気温が上昇し、甲府の今年最高を更新しました。朝日が注ぐ甲府盆地から富士山を望むことができました。
この日は約30人が参加し、4班に分かれてビニール張りをしました。各班が垣根4列分を仕上げたら次に移動する方式で、ビニールが張られると垣根の両側に1メートル間隔でパッカーを装着し固定していきました。
メルロ、シャルドネともヴェレゾンが進んでいます。
休憩時には中村一政名誉農場長からスイカの差し入れがありました。畑で良く冷えたスイカをほおばるのは格別でした。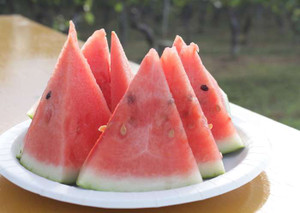
ビニール張りの後は、先週終わらせることができなかったシャルドネ畑での作業に着手。防鳥ネットの下部をバインド線で止めていきました。
筆者は昨年、ビニール張りで熱中症になりかけたので、ことしはネッククーラーを持参するなどより対策を強化。ただ、メンバーの手慣れた作業のおかげで、暑さが本格化する前にすべてを終わらせることができました。さて、これでメンバーが一堂に会する作業は収穫までないということです。
2025年08月02日|個別ページ
7月26日、メルロはヴェレゾン入りが確認できました。前日、7月に甲府で観測された猛暑日の日数は17日となり、観測史上最多を更新。甲府は連日、猛暑日が続いていて、高温によりブドウの色づきがやや遅れている印象です。撮影は、中村一政名誉農場長。
26日は防鳥ネットの設置作業をしました。
2025年07月26日|個別ページ
「日本ワインコンクール2025」(同実行委主催)で、山日YBSグループが栽培したシャルドネで仕込んだ「双葉シャルドネ2024」が、欧州系品種・白部門で銅賞を受賞しました。マンズワインが委託醸造しました。
コンクールは21回目で、31道府県の153ワイナリーから860点がエントリー。審査は7月9、10の両日、甲府市内で行われました。
同グループが栽培したブドウを使ったワインでは、2015年の日本ワインコンクールで、「双葉メルロー2013」が欧州系品種・赤部門で銅賞を受賞しています。
2025年07月25日|個別ページ
7月19日の作業は、房づくり、除葉でした。メルロのヴェレゾンはまだ確認できませんでした。
前日の18日、山梨を含む関東甲信が梅雨明けしました。県内の梅雨明けは平年より1日早く、昨年と同日でした。作業のこの日は、晴れて夏の富士山がくっきり見えました。
作業まずメルロからスタート。やや大きめの房は肩を落とし、垣根の東側のみ、房周りの2~3枚を除葉していきました。
写真はbefore & afterです。メルロ、シャルドネの順です。
メルロの後はシャルドネに移り、約4時間ですべての作業を終えました。
また、中村一政名誉農場長によりますと、7月12日、シャルドネの西側の畑で、べと病が確認されました。即座に、ベトファイター顆粒水和剤を散布して抑え込みました。
2025年07月19日|個別ページ
6月28日は房周りの副梢除去の作業でした。リポート、写真撮影はNNSの相山哲也さんです。
メルローの副梢取りは済んでいて、残りのシャルドネ全部が対象でした。
翌日に消毒の予定を組んでいるとのことで、今日中にすべての副梢取りを完了させることが最低ノルマでした。
午前6時から15人で取り組み、1回の休憩をはさんで午前9時過ぎには全て終了しました。この日は甲府で35.4度を観測し、2日連続の猛暑日となりました。
2025年06月28日|個別ページ
6月21、22日は土日とも作業でした。筆者は22日に参加しました。
メルロは果粒肥大期に入っていました。山梨県内は10日に梅雨入りしました。
作業は、まずメルロの摘心です。
続いて指導を受けた後、花カス取り、房周りの副梢除去、尻切りをしました。
来週も作業は続きます…
2025年06月22日|個別ページ
6月7日は作業日。シャルドネは幼果期に入っていました。
富士山が望める好天でしたが、朝からの気温の上昇が早く感じる日でした。
作業は、誘引の見直しです。まずはシャルドネから。なお誘引作業は5月24日、6月1日にも行われています。
続いてメルロ畑に移動。メルロは開花期に入っていました。
メルロは新梢の成長が早く、見直しといいつつ、また一から誘引といった印象でした。
マメコガネでしょうか。葉の食害を確認しました。ここは慣行農法ですので防除を待ちます。
2025年06月07日|個別ページ
記事・写真・イラストの無断掲載・転用を禁じます。Copyright 山梨日日新聞社 THE YAMANASHI NICHINICHI SHIMBUN.