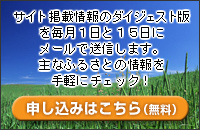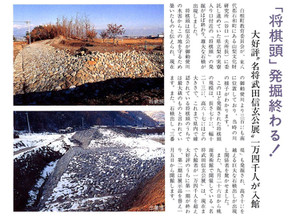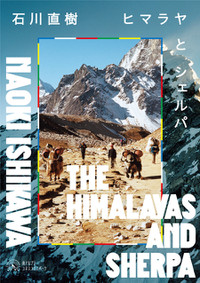2月に入り、節分、立春が過ぎ、暦の上では春を迎えました。しかし、2月11日金曜日、山梨県内は2014年(平成26年)以来の大雪に見舞われ、20cm以上の積雪を記録。桝形堤防も一面雪に包まれました。しかし春の陽ざしで雪解けも早く、着々と整備工事が進められています。


【写真】雪に包まれた桝形堤防
1.最新桝形堤防整備工事情報
(1)園路
舗装と植栽の間にウッドチップが敷き詰められました。ドウダンツツジの植栽を行う予定でしたが、雪解けを待って行う予定です。
(2)木工沈床の展示
発掘によって発見された木工沈床の一部を展示する区域に転落防止柵が設置され、その内部の保存と整備に着手しました。木工沈床は松丸太を井桁状に組んで中に石を詰める根固めの工法です(その2を参照)。周囲を囲む木材(方格材)は腐食し空洞となっているため、この空洞部分の復元方法が史跡保存整備委員会でも課題となりました。木材が腐食したため、石が移動し空洞が本来より狭くなっている状態のため、新たな木材を設置するためには全面的な石材の解体が必要となり、遺構本来の形状を崩すことになってしまいます。そのため、木工沈床の石が移動しないよう空洞を固定し、かつ現状復旧が可能な方法で、方格材を示すサインの役割を果たす方法を検討した結果、周囲の石材と全く異なる白色の玉石を充填することに決定しました。木材の代わりを玉石を使用することは誤解を招きやすい点については、解説版で説明することとしました。


【写真】木工沈床で空洞となった方格材痕に玉石を手作業で充填し固定しました。

【写真】木工沈床整備の完成
2.史跡整備の始まり エピソード0
このように一般公開を目指している桝形堤防の整備工事。現在に至るまで史跡がどのように発見され整備に辿りついたのか、その始まりまで遡ってみたいと思います。
「歴史や文化のないまちづくりなんてありえない」。名執齊一旧白根町長(故人)のこの言葉を、市文化財保護審議会の元会長である谷口一夫(故人)さんはよく覚えていました。当時帝京大学山梨文化財研究所長であった谷口さんは名執町長から依頼され、地域の文化遺産をともに踏査し、藪に囲まれた石積出を再発見したんですよと話されました。今から30年以上前のことです。

【写真】谷口一夫さん。市の初代史跡保存整備委員長も努め、石積出や将棋頭の発見、調査、指定、そして史跡の保存管理計画の策定に尽力されました
白根町では1988年(昭和63年)に放送された大河ドラマ「武田信玄」を契機に、歴史を活かした果樹観光に力を入れようとしていました。当時卓見だったのは、単なる地域の宝さがしではなく、学術的な調査が同時に行われ、遺跡の価値が考古学・歴史学の専門家によって検討が行われたことです。とりわけ昭和62・63年、白根町が帝京大学山梨文化財研究所に依頼した将棋頭の発掘調査は、全国でも韮崎市龍岡将棋頭に続く堤防遺跡の発掘調査であり、治水・利水研究史に残るものです。当時発掘調査を担当した宮澤公雄さんは、次のように当時を振り返りました。
「将棋頭は頭だけでていて、ほとんど埋まっていた。研究所に入って2年目で上司の谷口さんから言われて調査に入ったけれど、堤防遺跡は初めてで何が埋まっているかまったくわからず、手探りの調査でした。調査の結果、現在の将棋頭は戦国時代ではなく明治時代に修築されたものであることがわかりました。」

【写真】昭和62・63年度将棋頭の発掘を担当した宮澤公雄さん(現公益財団法人山梨文化財研究所)

【写真】昭和62年度将棋頭調査風景
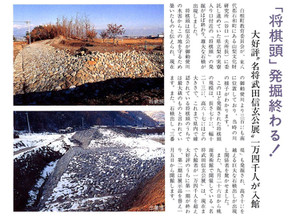
【写真】広報しらね 1987年(昭和62年)N0.216
残された将棋頭は武田信玄の時代の遺構ではありませんでしたが、発掘調査や文献調査の成果を基に当時の文化庁服部英雄文化財調査官の現地視察が行われました。谷口一夫さんとともに名執町長から文化財の調査を依頼された前史跡保存整備委員長萩原三雄さん(故人)は当時のことをよく覚えておられました。
「服部調査官が視察に来るということで、町長自ら将棋頭の前で待っていた。今でいうトップセールスだね。」

【写真】萩原三雄さん 谷口会長に続いて2代目の史跡保存整備委員長を努められ、昭和60年代の史跡の発見から指定、令和の桝形堤防の整備まで長期間に渡り南アルプス市の史跡整備をご指導いただきました
こうした調査成果や多くの人々の想いによって、国の指定史跡に向けて地域の意見がまとめられ、平成4年5月29日に文部大臣に意見具申が提出され、同年5月29日には国の文化財保護審議会において史跡指定の答申が出されます。それから十年余りの時を経て、平成15年3月25日、南アルプス市が誕生する直前に「御勅使川旧堤防(将棋頭・石積出)」という名称で、御勅使川を治めた堤防が国史跡に指定されました。河川堤防としては全国で2例目の指定であり、文字通り日本の治水・利水を代表する史跡となったのです。
平成14年には国土交通省と御勅使川・釜無川周辺の町村長や学術専門家らによって組織された「信玄堤懇談会」の調査によって、桝形堤防が発見されました。2002年(平成14年)7月10日付け山梨日日新聞の記事には「徳島堰守った堤防発見」と大きな見出しが掲げられています。当時帝京大学山梨文化財研究所所長だった萩原さんは「貴重な水を守ろうとした当時の人々の強い意思と知恵がうかがえる。甲州の治水・利水技術の歴史を考える上でも貴重」との証言しています。その12年後、この堤防は桝形堤防として国史跡に追加指定されることになりました(その1を参照)。

3.調査と活用
平成15年4月1日、芦安村、白根町、八田村、若草町、櫛形町、甲西町の4町2村が合併し、南アルプス市が誕生しました。この当時、合併によりさまざまな文化財行政の調整が必要で、すぐには史跡整備へ入ることができませんでした。その一方、南アルプス市が誕生するに当たり、文化財保護担当が市の文化財のテーマを話し合い、市の骨格の第一と考えられたのが「水」にかかわる歴史と文化でした。このテーマを基に、一歩づつ調査を進め、その成果をマップや史跡めぐり、講座などさまざまな形で多くの人に伝え活用を図る方針も固められました。特に小学校の授業や地域学習の核として石積出や将棋頭、桝形堤防は定番のコースとなっています。次に史跡にかかわるキーポイントとなった活用の事例をご紹介します。

【写真】遺跡で散歩 御勅使川ゆかりの史跡を歩く。文化財ウォーキングマップの第1号


【写真】小学校4年生 石積出三番堤社会科見学時、史跡の清掃体験を毎年行っています。
(1)史跡指定10周年記念シンポジウム「てっすげえじゃんけ将棋頭・石積出!」
2013年(平成25年)には史跡指定10周年記念シンポジウム「てっすげえじゃんけ将棋頭・石積出!」と題し、史跡をはじめ歴史を活かしたまちづくりを市民のみなさんと築いていけるよう、二日間のイベントを行いました。史跡めぐりあり、竹蛇籠体験学習あり、講演あり、市民トークあり、クイズあり、歌あり、笑いあり、涙あり、みんなのわくわくを目指した試みでした。
詳しくは記録集(PDFダウンロード)をご覧ください。
1日目
御勅使川旧堤防(将棋頭・石積出)国指定10周年記念
~御勅使川ゆかりの史跡を歩く~
小雨のため、バスで石積出や桝形堤防、将棋頭をめぐりました。
2日目
ふれあい情報館を会場に展示スペースを設けました。外ではかつて治水に用いられていた「竹蛇籠」づくりの実演と体験教室、そして史跡を除草してくれているヤギさんとのふれあいコーナーを設けました。
午後からは会場全員で御勅使川縦断ウルトラクイズ、次に文化庁の佐藤正知主任調査官と山梨県教育委員会の森原明廣さんの講演、さらに文化財担当者二人の掛け合いで「なるほど講座 将棋頭・石積出ってなあに?」、つづいて史跡にかかかわる人々のリレートーク「みんなでかたろう まちづくり劇場」を行いました。
(2) 平成28年度全国史跡整備市町村協議会(全史協)東海地区協議会総会・研修会を南アルプス市で開催!
東海地区の県や市町村の首長や史跡整備担当者が集まり、研修会を開催。文化庁からは水之江和同調査官に「史跡を活かしたまちづくり」と題してご講演をいただきました。また甲府城や北杜市梅ノ木遺跡など県内の史跡整備先進事例についてそれぞれの担当者の方に発表していただきました。二日目の現地視察では、石積出で白根飯野小6年生が史跡を劇で紹介、将棋頭ではこの堤防で守られてきた水田のお米でにぎられた将棋頭おむすびも味わっていただきました。

【写真】白根飯野小学校6年生 事前学習で歴史を学び、それを体で表現しました

【写真】東海地区の文化財担当者を前に胸をはって史跡を解説するこどもたち

【写真】将棋頭では将棋頭で守られてきた水田で育てられたお米のおむすびをご馳走!五感で史跡を感じてもらいました。海苔の形に注目してください

【写真】将棋頭おむすびを撮影、味わう参加者。お米は「イセヒカリ」という風水害に強い品種で、食感はもっちりしています
(3)平成30年度第53回全史協甲府市大会エクスカーション
平成30年10月4日行われた全史協甲府市大会のエクスカーションで石積出と桝形堤防などの現地視察が行われました。全国から集まった市の首長や文化財の担当者を前に、石積出三番堤では、その仕組みや歴史、次世代へつなぐ大切さを地元の白根源小6年生が劇で表現しました。また、桝形堤防では90歳の矢崎静夫さんが水争いの体験談をユーモアをまじえて話されました。53年続く協議会でも、こうした地域の人々によるプレゼンテーションは初めてのことだったかもしれません。

【写真】白根源小6年生が石積出や守られている村々、洪水流を表現。全史協で披露された劇は、水を求め水を制した歴史を音と映像を交えスケールアップされ、学習発表会で地域の方に披露されました。劇は現代と江戸時代を行き交うフアンタジーで、観客は子どもたちの芝居に惹きこまれていました。学年の最後には学習内容を○博のデジタルアーカイブにアップし、「水の源」を世界へ発信しました

【写真】史跡を学ぶ側から伝える側へこどもたちが変わった瞬間です

【写真】桝形堤防では史跡の除草に活躍するヤギも二頭?登場。地元農業NPOと協力して除草を行っている経緯や効果、ヤギによる除草のメリット・デメリットの解説がヤギさんの言葉で解説されました

【写真】桝形堤防の分水門で昭和30年代まで行われていた地域の水争いを当時90歳になる矢崎静夫さんが会員に説明。方言を交えユーモアに富んだ解説に、みな喜んでいました。現代でも使われつづけている桝形堤防の歴史ならではの証言です
3. 水の世紀を生きる道標(みちしるべ)
かつて南アルプス市域では日常的に干ばつが起こり、大雨が降ると洪水に襲われました。堤防を整備し、水路を整えては洪水に流され、新たな技術でまた造り直す。この営みを現代まで続けてきた地域です、まさに水とともに生きてきた人々の営みの結晶が石積出や徳島堰と桝形堤防、六科将棋頭などの史跡と言えるでしょう。

【写真】昭和34年 御勅使川の洪水によって流される芦安中学校
現代世界そして日本では気候変動や生活様式の変化に伴い、干ばつと洪水が頻発しさらに水資源の争いが増加すると予想されています。その時代を生き抜くため、世界に貢献できる知恵と技術が南アルプス市には残されています。3月にはJICAによるベトナムの人々の砂防・治水の研修で石積出や桝形堤防を訪れることになっています。史跡御勅使川旧堤防(将棋頭・石積出)とそれに関連する地域に残された水の文化や記憶がこれから進むべき道標ともなるのです。

【写真】石積出三番堤:2023年1月30日重要遺跡発掘調査によって初めて姿を表した石積出三番堤の基底部。径約0.8~1mの巨石が石積に使われている

【写真】六科将棋頭:中央の水路は桝形堤防で分水された徳島堰の水を運ぶ後田堰

【写真】空から見た桝形堤防。治水・利水・防災など水にかかわる歴史が積み重なり、現代に続いています
過去を学ぶだけでなく、過去に学ぶ。多くの人々がつないできた史跡の保存。今、これからの生き方を考える史跡整備を目指しています。
【南アルプス市教育委員会文化財課】