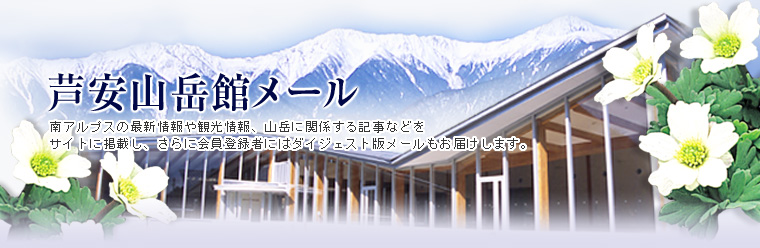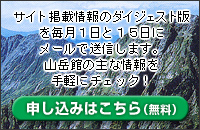南アルプス世界自然遺産登録山梨県連絡協議会は19日、南アルプス市櫛形生涯学習センターで、トークショーなどで南アルプスの魅力を紹介する「南アルプス休日山歩」を開いた。
若者に山についての関心を持ってもらおうと企画。女優で登山雑誌のモデルも務めるKIKI(キキ)さんや、登山系のイラストレーターなどで活躍する鈴木みきさんをゲストに招いた。
トークショーでは、2人が一緒に登った仙丈ケ岳の写真を披露し、「頂上からは富士山と北岳が重なった景色を望むことができる。氷河の跡として残っているカール地形も楽しめる」と紹介した。
来場者との質疑応答では、これまで山と関わってきた経験を基に、キキさんが「南アルプスは登るたびに新たな魅力を発見することができる」と話し、鈴木さんは「山を通じていろいろな人と出会うことができている」と笑顔で語った。
静岡大理学部の増沢武弘特任教授や南アルプス芦安山岳館の塩沢久仙館長らによる「南アルプスの魅力ってなんだ?」と題したパネルディスカッションもあった。
【山梨日日新聞社 2月20日掲載】