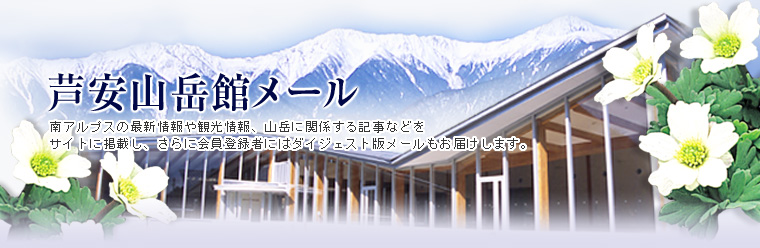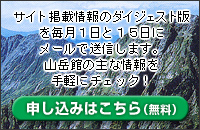春夏秋冬、その季節ごとにさまざまな風景を見せてくれる芦安堰堤(えんてい=堤防、ダム)をご紹介します。
芦安堰堤は、明治時代以降、河川における砂防の重要性が唱えられ、特に明治40年の大水害以来、国の直轄により御勅使川下流の土砂災害を防ぐため、当時の最先端の工法によって旧芦安村芦倉に設置されたものです。この堰堤は、日本の大砂防堰堤7基のうちに入っており、我が国で最初にコンクリートを利用した砂防堰堤で、下部(重力式)と上部(アーチ式)の異なる構造を併せ持つ珍しいものです。
大正5年12月に起工、重力式堰堤が大正7年に完成します。その後、大正13年にその上部にアーチ式堰堤を増設し、大正15年に完成しました。この増設によって当時国内で最も高い(22.6メートル)砂防堰堤となり、これにかかった建設費は当時の金額で約9万6000円(現在の金額に換算すると5億円以上)といわれ、その半分がセメント代だったといいます。
県は当時のままの状態で現在も有効に機能していることから、貴重な歴史的建造物と認定し、平成9年に文化財に登録されました。
今回は冬の芦安堰堤の写真を掲載しました。堰堤をより一層引き立ててくれる木々は、今は寒々しい姿ですが、芽吹きの春にはやまぶき色に、夏は新緑の濃い色とやまぶきの花に包まれ、秋は紅葉に染められ-と、四季それぞれ違った姿を見せてくれています。
ぜひ芦安堰堤に足を運んで、この堰堤が私たちの生活にどのように関わりを持つかなど考えたり、魅力を感じていただければと思います。