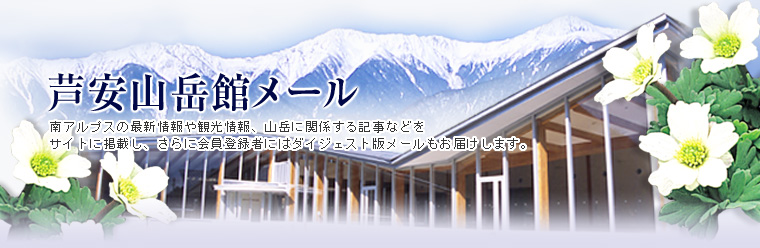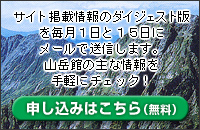今回は、芦安が原産地とされている「甲斐犬」についてご紹介します。
甲斐犬は日本犬の一種で、1924(大正13)年に小林承吉(元甲府動物園長、獣医師)が発見、1930(昭和5)年「甲斐日本犬」と命名発表し、1934(昭和9)年1月22日、秋田犬に次いで天然記念物に指定されました。
原産地は南アルプス市(芦安地区)、早川町、山梨市(牧丘地区)、身延町(下部地区)などの山間地で、険しい山の岩場でカモシカを獲っていたという、俊敏な動作で跳躍力が優れた日本犬です。
 |
| 【写真】「甲斐犬の里」の看板 |
発見当時、甲斐犬にはカモシカ猟に使用された「鹿犬型」と猪猟に使用された「猪犬型」の2つの体型がありました。「鹿犬型」の特徴は細身で体は長め、垂直に飛び上がる力に優れています。それとは対照的に、「猪犬型」は胴が太め、体は短めで真っ直ぐに突き進む力に優れています。残念ながら「猪犬型」は第二次世界大戦中に絶滅してしまって、現在は「鹿犬型」しか存在していません。
甲斐犬を発見した当時、芦安地区の成人男性のほとんどが狩猟をしていたということで、当時の人たちにとっては大切な家族だったのではないかと思います。非常に賢く、一説ではシェパードよりも優秀と言われていて、性格は主人と家族にとても忠実で素朴な犬です。
現在芦安には、純血種の甲斐犬が何頭か飼われていますが、その中から今回は伊井さんのお宅にお邪魔して甲斐犬の写真を撮らせていただきました。こちらのお宅には現在7頭の純血種の甲斐犬がいて、雄と雌それぞれに手作りの立派な犬舎があります。伊井さんが写真のモデルとして選んでくれたのは雄の永遠(とわ)くんと強(ごう)くんの親子でした。2頭ともクマさんのような可愛い顔で、つぶらな瞳で飛びついて来る様子からとても人懐っこい感じを受けました。


【写真・左】子どもの強くん(左)お父さんの永遠くん 【写真・右】手作りの犬舎
全身が甲斐犬の特徴である虎毛色で、聴力が優れているという大きな三角形のピンと立った耳が、賢さを表してるようでした。飼い主の伊井さんが「犬も家族だから、たくさんいてもすぐにどの子か分かるよ」と話す言葉から、大切にしている様子が伝わってきました。
 |
| 【写真】日なたぼっこをするお猿さん |
甲斐犬のかわいい写真を撮った帰り道に、芦安名物の「日なたぼっこ」をする猿の群れと遭遇し、なんとか一匹だけカメラに収めることに成功しました。日に当たりながらうっとりしている猿の群れに、とても癒されたひとときでした。