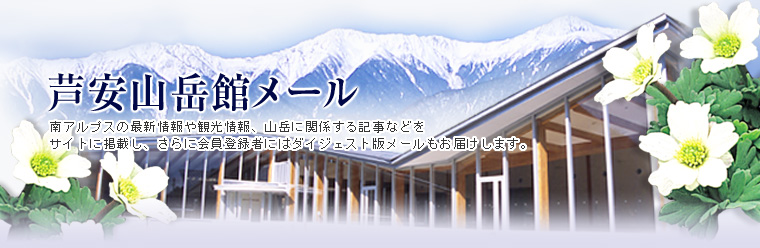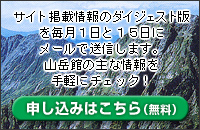【写真・左】11月29日 夜叉神峠 【写真・右】12月9日 山岳館周辺の山
今回は11月29日に山岳館の方と訪れた夜叉神峠へのハイキングの様子をお伝えします。
夜叉神峠登山道はルートが分かりやすく危険な場所もほとんどないので、子ども連れでも大丈夫です。往復1時間50分ほどで登れるハイキングコースとしてとても人気です。峠までの道はかつて、芦安村の人々が狩猟や炭焼き、林業などの生活の糧を得る仕事場へ往来してきた大切な道でした。
山岳館から車で15分ほど登ると夜叉神の登山口がある夜叉神の森駐車場に到着します。こちらは鳳凰三山の登山口にもなっています。平日で紅葉の時期も過ぎてしまった事もあってか、駐車場には数台の車が駐車していました。
準備を整え登山口まで行くと、皇太子殿下の記念碑が迎えてくれます。少し急な登りを歩いて行くと昔の人々が斧や銃を持って山に入っていた姿を想像してしまうような「炭窯跡」や、山の神を祭った小さな祠(ほこら)を見つけました。急な登りを越えるとなだらかな道が続きます。道は枯葉に覆われていて落ち葉のじゅうたんのようでした。
 |
| 【写真】炭窯跡 |
お花や紅葉の時期も終わってしまい、枝だけになってしまった木々の間から甲府盆地や櫛形山を望み、今の時期にしか味わえない素晴らしい景観がありました。ブナやクリ、ミズナラなどの木々の間を歩くと、幹が根元で五本に分かれたカラマツ「五本松」が現れました。根元はかなりの太さなので、相当な樹齢だろうと思いました。
五本松まで来ると夜叉神峠まであと30分です。そこからは笹の生い茂る間を歩いていくのですが、小石が転がる音にカサカサ、サワサワと心地良い笹の触れ合う音が加わってきました。下を見ると笹のあちこちに霜が付いていて、陽の光に当たるとキラキラしてとてもきれいです。前方のカラマツの木の枝にトロロのような物がたくさんぶらさがっていました。このトロロのような物は「サルオガセ」といって湿り気のある枯れた木に寄生して空気中の水分を吸収し、光合成を行なって生きている寄生植物だと聞きました。なんとも言えないその雰囲気からホラー映画に出ていたのを思い出し、霧がかかった日には良く似合うだろうなと感じました。
少し登ると見晴らしのいい場所に出ました。ここが高谷山との分岐点です。余裕がある人は往復1時間ほどの高谷山まで行くコースもオススメです。今回は時間があまりなかったので高谷山には行かず夜叉神峠を目指しました。この日は朝から快晴だったのできれいに白峰三山が見えると期待していたのですが、山々の頂きには雲がかかっていて、雪が降っているようでした。白峰三山の絵を描いている方と「きれいに見えなくて残念でしたね」と話し、またリベンジしようと決めました。
帰り道では鳳凰三山を縦走した人たちと出会ったり、富士山の頂きが見えるポイントを発見したり、40分ほどで駐車場に到着しました。
12月8日に降った雪で山岳館から見える山々の頂きが真っ白になりとてもきれいです。これから芦安の里や周りの山の変化していく様子が楽しみです。
[南アルプス芦安山岳館スタッフ]