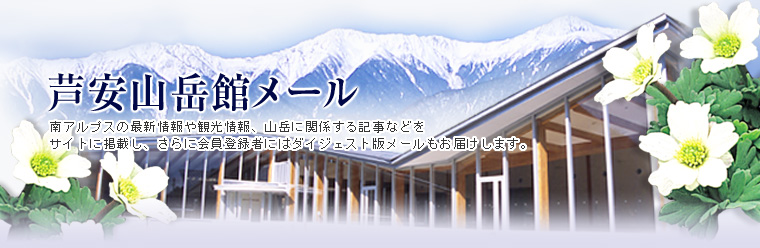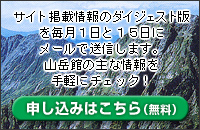南アルプス市の芦安小、芦安中が4月から、「英会話科」の授業を独自に始める。国の制度を活用し、「総合的な学習」などの時間を英会話の授業に振り替え、中学校卒業までに英語で日常的な会話ができるレベルを目指す。児童・生徒数が少ない教育環境を逆手に取り、マンツーマンに近い形で指導を受けられることをアピール。学区外からも入学生を募って児童・生徒数を増やす狙いもある。「過疎の学校」の試みは成功するのか。市教委関係者は期待をかけている。
 「少ない人数の中で充実した英語の指導が受けられそうだ」。昨年12月、入学を希望する保護者と市教委の面談会。母親は自宅に近い中学校ではなく、山あいにある芦安中を選択した理由をこう説明した。
「少ない人数の中で充実した英語の指導が受けられそうだ」。昨年12月、入学を希望する保護者と市教委の面談会。母親は自宅に近い中学校ではなく、山あいにある芦安中を選択した理由をこう説明した。
芦安小、中の児童・生徒数は過疎化に伴い減少し続けている。小中合わせて約200人が在籍した時代もあったが、1月現在の児童・生徒数は芦安小が25人、芦安中が10人。1学年の子どもの数が国の学級基準を下回っているため、市独自に教員を配置し、複数の学年を1人の教師が指導する複式学級の解消を図っている。
児童・生徒数を増やし、往時の活気を取り戻すことができないか。旧芦安村時代の1994年には山村留学施設「南アルプスチロル学園」を開園し、首都圏などから子どもの受け入れを始めた。しかし、厳しい財政状況を踏まえ、3月末で閉園することが決まっている。
こうした中、南アルプス市教委が着目したのが、学習指導要領で定めた教育範囲とは別に、特別なカリキュラムを組める特例校制度だ。県内では山梨市が認定を受け、市内4小学校で1年生から英語の授業をしている。
全国では、宇都宮市の山沿いにある城山西小が2005年、「会話科」を導入。英語や日本語での会話力養成に重点を置いたカリキュラムを編成した結果、保護者の関心が集まり、05年度に35人だった児童数は、12年度には3倍近い91人まで増えた。
南アルプス市教委によると、英会話科の授業では小学1年から、外国語指導助手(ALT)や担任の教諭が指導に当たり、カードや手遊びなどゲーム形式の授業も取り入れ、楽しみながら英語を学ぶ。授業時間は生活科や音楽科などを振り替え、年間15時間を確保。1クラス数人という「少人数学級」の中、担任教諭やALTらが1対1に近い形で指導に当たる。
市教委が昨年11月に開いた説明会には約20人の子どもの保護者が出席。担当者との面談で、保護者は「英語で歌を歌うなどの取り組みに魅力を感じる」「豊かな自然の中で、充実した英語教育を受けられる」と期待感を示した。
ただ、市内の中心部から車で片道25分程度はかかるという通学距離がネックだ。市教委はスクールバスを運行せず、保護者に送迎してもらう考えで、説明会に出席した保護者の多くが送迎できないことを理由に入学を見送った。
4月には、市内の児童・生徒4人程度が学区外から入学する見通し。芦安地区の子どもと合わせた芦安小、中の入学生は10人程度で、いつもより少しにぎやかな入学式になりそうだ。横小路允子教育長は「英会話科の導入をきっかけに、自然体験ができるといった特色も知ってもらい、学区外からの入学生が増えることを期待したい」と話している。
(写真)4月から英会話科の授業を始める芦安中。生徒数が少ない教育環境を逆手に取り、きめ細かい指導が受けられることをアピールして学区外から入学生を募る考えだ=南アルプス・芦安中
【山梨日日新聞社 1月27日掲載】