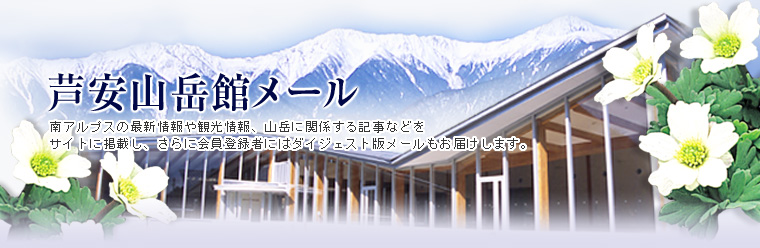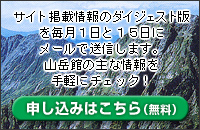本年度で留学生受け入れ制度の廃止が決まり、閉園する南アルプス市芦安芦倉の山村留学施設「南アルプスチロル学園」(深沢秀学園長)は9日、卒園生や元職員らを招いて交流会を開いた。参加者は在籍当時の文集やアルバムなどを見返しながら、閉園を惜しみつつも、久しぶりの再会を喜び合った。
 交流会には首都圏や県内から約80人が参加。手作りした煮物や菓子などを食べながら、現状報告や、サクランボ狩りやスキー、夜叉神峠登山などの思い出話に花を咲かせた。卒園生ら約60人から寄稿を募り閉園に合わせて制作した記念文集も配布。文集には「私の原点」「最高の思い出」「今までありがとう」などの言葉が並び、学園への感謝の気持ちがつづられていた。
交流会には首都圏や県内から約80人が参加。手作りした煮物や菓子などを食べながら、現状報告や、サクランボ狩りやスキー、夜叉神峠登山などの思い出話に花を咲かせた。卒園生ら約60人から寄稿を募り閉園に合わせて制作した記念文集も配布。文集には「私の原点」「最高の思い出」「今までありがとう」などの言葉が並び、学園への感謝の気持ちがつづられていた。
横浜市出身で、学園で中学校時代を過ごした田中貴浩さんは「たくさん思い出がある。大学卒業後、山梨に戻ってきたいと思わせてくれた場所。さみしい気持ちはあるが、仲間との交流は続けたい」と笑顔で語った。
最後の卒園生となる芦安中の西沢志真人君は「共同生活を通じて大切な仲間ができた。来年度は神奈川に戻ることになると思うが、学園での経験を生かして頑張りたい」と前を向いた。
同学園は、都会の小中学生の受け入れを目的に1994年に旧芦安村が開園。これまでに首都圏を中心に約200人を受け入れて、都会の子どもたちが親元を離れて施設で寝泊まりしながら、芦安小・中に通学。地域との交流を深めてきた。だが開園当初20人ほどだった入園者数は次第に減り、現在の在籍者は7人にとどまっている。
芦安地区からは「地域で子どもたちとふれあう機会が少なくなる」などと存続を求める声があったが、留学生の減少や厳しい財政状況などを踏まえ、市教委が留学生受け入れ制度の廃止を決めた。
深沢学園長は「地域の人の温かい支援があって、ここまで継続してこられた。卒園生には学園のことを忘れずに、目標に向かって頑張っていってほしい」と話した。
(写真)アルバムを見ながら思い出話に花を咲かせる参加者=南アルプス市芦安芦倉
【山梨日日新聞社 12月14日掲載】