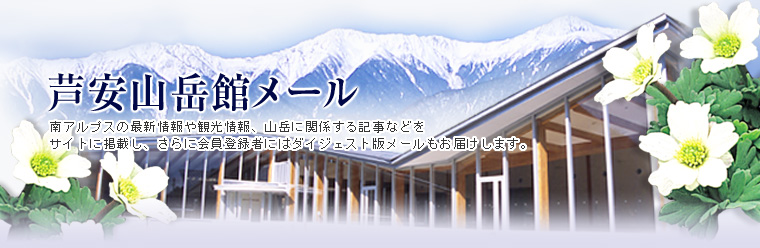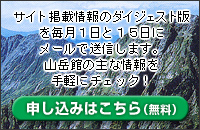「人はなぜ山に登るのか」そんな壮大なテーマに挑んだ平成24年度の企画展「南アルプス 登山史を探る」が6月15日に開幕しました。当日は、南アルプス市の中込博文市長をはじめ、約80名の来賓、関係者が出席し、セレモニーが行われました。
 |
 |
展示室に向かうと、まず横幅6メートルの白峰三山の雄大な写真が目に飛び込んできます。北岳・間ノ岳・農鳥岳の写真をじっくり鑑賞した後、展示室に入ると、南アルプスの山々を舞台にした登山の歴史を、縄文時代から現代にわたって紹介しています。また、地蔵岳で発見された懸仏や日本近代登山の父ウオルター・ウエンストン氏の原書、北岳の三角点などの貴重な展示品を、白簱史朗氏の素晴らしい写真とともに鑑賞できます。
 |
 |
縄文時代から現代まで、さまざまな時代背景の中で、人々は山に対してどのような考えをもち、何を感じ、どのように山と関わってきたのかを南アルプスを切り口にして探り、そして、これからの私達はどのように山と関わっていくのか。未来に向けた南アルプスの姿を皆さんとともに考えていきたい、そんな展示になっています。ぜひこの機会に南アルプスの山々の歴史をじっくりと見つめていただきたいと思います。