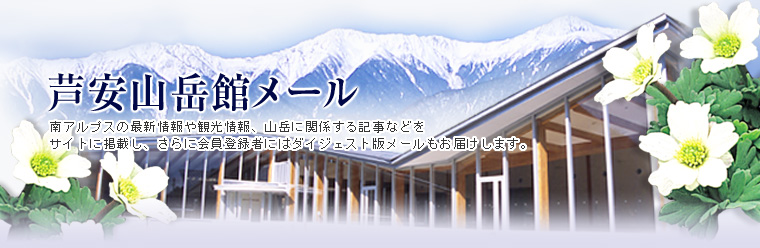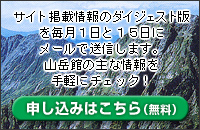今回も、前回に引き続き芦安の歴史や史跡をご紹介します。今回出会ったのは芦安の小曽利と大曽利地区にある「六地蔵」です。
 |
| 【写真】小曽利地区の「六地蔵」 |
最初に小曽利地区の「六地蔵」を探しに行きました。芦安の史跡に詳しい地元の方に案内していただいたのですぐに見つかりましたが、一人では発見できなかったのではないかと思います。民家に挟まれた狭い場所にあり、高さ38センチほどのこじんまりとした、かわいらしいお地蔵様で、六体が一つの石の中に収まっています。
六地蔵とは、「文珠菩薩」「普賢菩薩」「日光菩薩」「月光菩薩」「虚空蔵菩薩」「地蔵菩薩」の六菩薩を称して六地蔵と言います。人間が現世から来世に渡った時、人間界での生き方により、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間界、天上界の六道にそれぞれ分別されると言われています。六地蔵は、この分別された六道のそれぞれの入り口に一体ずつ立っていて、地獄や餓鬼などのつらい道に落とされた者にも救いを施してやろうという慈悲を表している仏だといわれています。このため、人々は現世のうちにこれを祭り、来世に行った時に苦難から逃れられるようにと、真剣に祈りを捧げたという事です。
芦安の歴史は古く、江戸時代の1604年に芦安村が誕生する前の「芦倉村」と「安通村」の存在が記録されていて、現在の芦安は明治8(1875)年に両村が合併し、誕生しました。誰がいつどんな想いでこの「六地蔵」を置いたのでしょうか。
 |
| 【写真】大曽利地区の「六地蔵」 |
続いて大曽利地区の六地蔵を探しに行きましたが、急な坂道の細い路地で、こちらもたどり着くのに少し苦労しました。こちらは、お地蔵様の原形は既になく、ただの石の塊になっていて、周りは道祖神などの石で囲まれています。小曽利地区のものとはだいぶ状態が違っていました。近くでよく見ると頭と思われる形が残っているのが分かりました。その様子からかなりの年数が経っていることが分かります。形のなくなった現在でも大切に祭られていることから、芦安では地蔵信仰がしっかり受け継がれているのだと感じました。
 |
| 【写真】山岳館にあるお地蔵さん |
六地蔵の他にも芦安にはいくつかのお地蔵様があるので、今後も皆さんにお伝えしていきたいと思います。山岳館にも私が木で作ったお地蔵様がいるので、芦安に来た際には会いに来ていただけたらうれしいです。